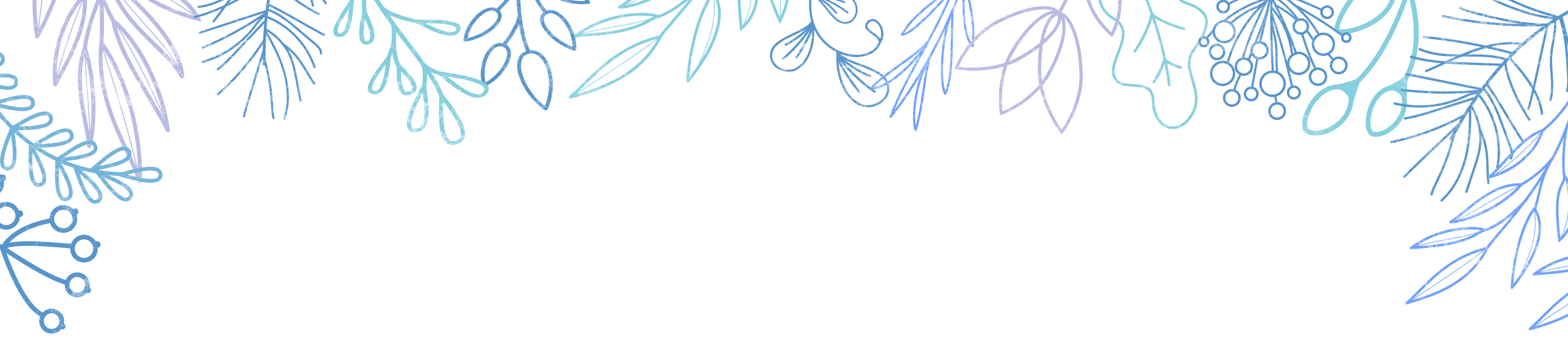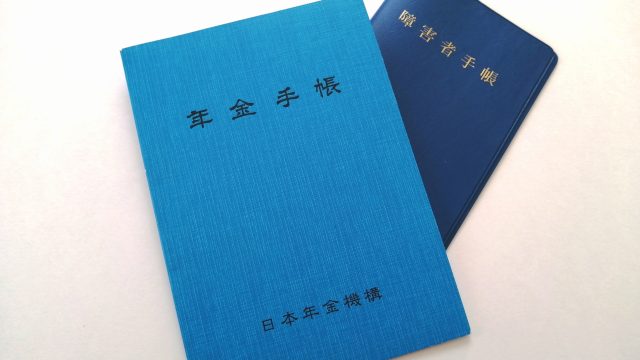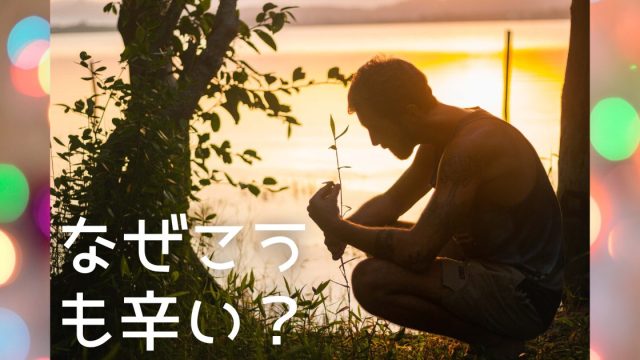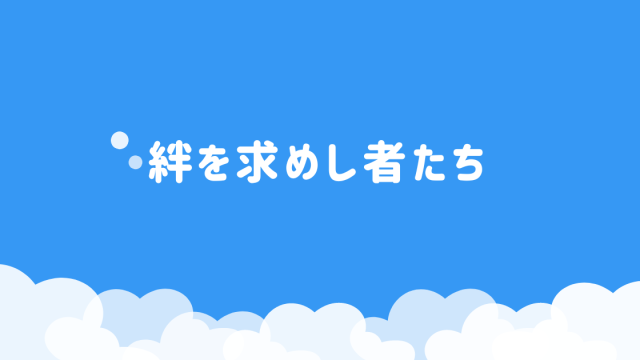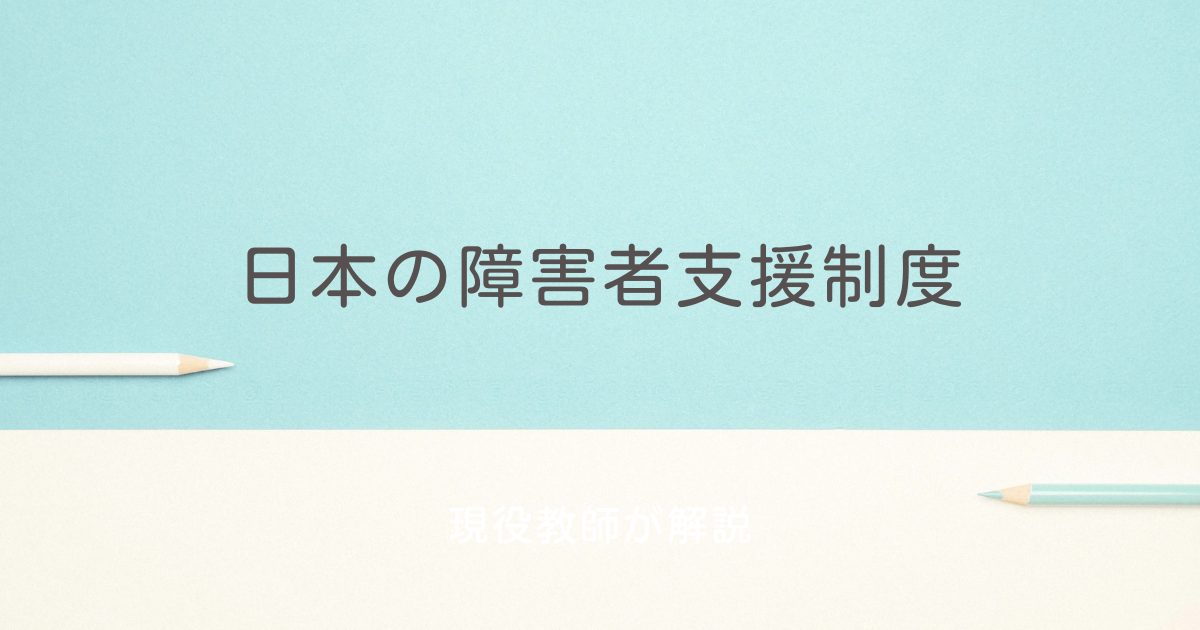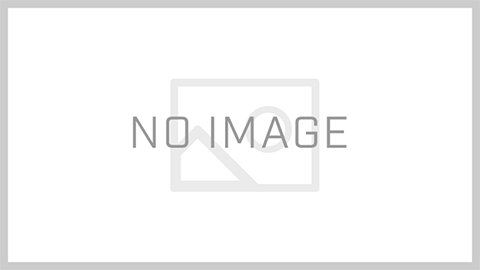支援のバリエーションは増えてきてる
発達障害の診断数増加や境界知能の認知度が高まってきたことにより、当事者を支援する手段が多くなっています。
境界知能自体に特化した施策はまだ無いのですが、現在の国や自治体が展開している制度を使えば特性に配慮した支援を受けられることは十分可能です。
ここでは国が行っている支援策を紹介します。
- 特別支援教育
- 相談窓口
- 就労支援
- 障害者雇用制度
特別支援教育について
障害のある児童生徒に個別のニーズに応じた教育を行い、主に「特別支援学校」と「特別支援学級」の二種類があります。
障害による学習または生活の困難を克服し、社会的自立を促進させることが目的のため、障害の特性に考慮した授業を受けることが出来ます。
一般的に境界知能(グレーゾーン)は知的障害と診断されることがないため診断名がつかず、特別支援教育の対象にならないため結局普通学級で過ごすケースが多くあります。
しかし近年は認知度が高まってきた影響により、比較的グレーゾーンでも特別支援教育を受けるべきとの声も上がってきています。
特別支援学校に入学または学級に入るには、心理士による知能検査を受けてその結果を学校や教育委員会に共有すれば支援と結びつく可能性があります。
もしも検査を受けても障害じゃないから支援の必要なしと学校側に言い渡された場合、後述の相談機関に打ち明けてサポートをしてもらうのも有効です。
- 障がいのある児童生徒に対して、個別のニーズに応じた教育が行われている
- 1学級あたりの児童生徒数は、原則として8人以下
- 障がいの特性に応じた専門的な設備や教材が整備
- 発達障害のある児童生徒を支援する体制が普通学級よりも強化されている
各相談窓口
生活や就労で困難がある人を支援する機関が様々あり、下記の窓口に相談すれば悩み事が解決し、境界知能恒例の生き辛さをある程度緩和するきっかけになると思います。
まずは「今自分は生き辛くて困ってるんだ」と発信して、助けを求めてみましょう。
- 障害者就業・生活支援センター
- 福祉事務所
- 保健所
- 児童発達支援センター
- 特別支援教育センター
- 発達障碍者支援センター
就労支援の強化
発達障害の就職をサポートする施策が強化されてきたおかげで、以前よりもハンディのある人の就職がしやすくなってきています。
国は障害者雇用にも力を入れており、障害者を雇用した企業に対し助成金制度などを設けています。
そのため企業側にとっても障害者を採用する事は、多様性の拡大や外注費の削減などの様々なメリットがあり、採用された側も働き口を見つけた上に職場に定着できれば障害があっても社会貢献できるという自信につながります。
就労支援を受けるには障害者手帳が必要になりますが、医師の意見書があれば手帳がなくても申請できます(その場合は自治体で障害福祉サービス受給者証を申請する必要があります)。
- ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどと連携
- 職業訓練や職場実習などを通して、就労に必要なスキルを習得する機会を提供
- 就労移行支援事業所など、就職するためのサポートを行う機関
まとめ
境界知能は障害者手帳を取得が出来ず、障害者として認定されないことが多くあるため、公的な試験を受けるのが難しいケースが非常に多くあります。
しかし知名度が高まった影響により支援の必要があると理解されるようになり、数十年前よりも支援を受けやすくなってきています。
できるだけ特性を早く発見し、専門機関などを通して早期に支援を受ける事が生き辛さを緩和する事に繋がります。
また障害者手帳がなくても医師から意見書をもらえば、福祉制度を利用することもできます。
まず利用できそうな支援制度があれば気軽に使ってみるくらいの気持ちで申請してみましょう。